MQ会計の全体像:企業方程式と要素法で読み解く利益構造
MQ会計とは?通常の会計との違いとビジネスでの活かし方
1. MQ会計とは?
MQ会計とは、西順一郎氏が提唱する経営分析の手法であり、特に利益構造の理解を深めるための会計手法です。MQは、売上総利益(粗利益)を表します。この考え方は、企業の収益性を高めるために非常に有効です。
2. 通常の会計との違い
一般的な財務会計では、売上高・売上原価・固定費・変動費・利益などの指標をもとに決算を行います。一方で、MQ会計では以下のような特徴があります。
付加価値(MQ)の重要性
通常の会計では、売上総利益や営業利益を重視しますが、MQ会計では「売上総利益(MQ)」を経営の中心とします。
- MQ = 売上 – 変動費 で計算され、企業の成長や利益拡大のための基礎指標となります。
固定費と変動費の明確な区分
MQ会計では、コストを固定費と変動費に厳格に分けることで、経営判断の指針を明確にします。
- 例えば、変動費の管理によってMQを向上させ、固定費のコントロールによって収益を最適化することが可能になります。
意思決定に直結するシンプルな計算方法
MQ会計は、経営者や現場のリーダーが素早く判断できるようにシンプルに設計されています。
- 複雑な財務会計に比べ、短期間で学び、活用しやすいのも特徴です。
3. P,V,Q,F,Gの要素法とは?
MQ会計では、利益を構成する主要な5つの要素として P(売価)、V(変動費)、Q(数量)、F(固定費)、G(利益) を重視します。
- P(Price/売価):販売価格をどのように設定するかが利益に直結する。
- V(Variable cost/変動費):仕入れコストや製造コストの管理がMQ向上に影響を与える。
- Q(Quantity/販売数量):販売量の増加が直接MQに影響する。
- F(Fixed cost/固定費):適正な固定費の管理が利益を確保する鍵となる。
- G(Gain/利益):P,V,Qのバランスを最適化することで、G(利益)を最大限に獲得することが重要。
4. 企業方程式とMQの関係
MQ会計では、利益をシンプルな数式で考え、経営の意思決定をサポートします。以下のような基本方程式が使われます。
- PQ = VQ + F + G(企業方程式)
- 売上高(PQ)から変動費総額(VQ)と固定費(F)を引いたものが利益(G)となる。
- PQ – VQ – F = G
- 企業方程式の変形によって利益(G)の算出が可能。
- P – V = M(マージン、付加価値)
- P(販売価格)からV(変動費)を引いたものがM(マージン)となる。
- M × Q = MQ(粗利総額)
- M(1個あたりの粗利益)にQ(販売数量)を掛けるとMQ(粗利総額)になる。
- PQ – VQ = MQ
- 総売上(PQ)から変動費総額(VQ)を引いたものがMQとなる。
- MQ – F = G(営業利益)
- MQからF(固定費)を引いたものが最終的な営業利益となる。
この企業方程式を活用することで、利益を最大化するための具体的な戦略が立てやすくなります。

5. MQ会計をビジネスで活かす方法
(1) 価格戦略の最適化
MQを理解することで、価格設定が利益にどのように影響するかを明確に把握できます。価格変更がMQに与える影響を考慮しながら、利益を最大化する戦略を立てることが可能になります。
(2) 利益率の向上
MQを高めるためには、変動費の見直しや付加価値の向上が重要です。例えば、仕入れコストの削減や生産効率の改善によって、より高い限界利益を確保できます。
(3) 固定費のコントロール
固定費が大きくなりすぎると、MQが向上しても利益が残りにくくなります。適切な固定費の管理を行いながら、MQの最大化を目指すことで、安定した経営が可能になります。
(4) 事業拡大の意思決定
新規事業の展開や設備投資を検討する際、MQを基準に判断することで、長期的に利益を確保できる事業戦略を立てることができます。
6. まとめ
MQ会計は、単なる財務管理手法ではなく、経営の意思決定に直結する実践的なツールです。P,V,Q,F,Gの要素法と企業方程式を活用することで、売上やコストの管理だけでなく、利益を生み出す構造を理解し、企業の成長を加速させることができます。次回は、MGを通じて学ぶ「利益の本質」について解説します!


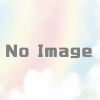
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません