MG5期をプレイして学ぶ「利益の本質」
前回までのブログでは、MG(マネジメントゲーム)の概要や、MQ会計の全体像について解説しました。今回は、MGを実際に5期プレイすることで学べる「利益の本質」に焦点を当てます。
1. MGの5期をプレイする意義
MGでは、1期ごとに経営の意思決定を行い、決算を繰り返しながら5期分の経営を経験します。プレイヤーは、
- 価格(P)を設定し
- 変動費(V)を管理し
- 数量(Q)を増やす工夫をし
- 固定費(F)をコントロールする
といった、実際の企業経営に必要な要素を学びます。
2. 企業方程式を活用した利益構造の理解
MGでは、以下の企業方程式を使って利益の構造を分析します。
PQ = VQ + F + G
- PQ(売上) = P(価格)× Q(販売数量)
- VQ(変動費総額) = V(変動費単価)× Q(販売数量)
- F(固定費) = 毎期発生する固定的な費用
- G(利益) = 売上から変動費と固定費を差し引いたもの
この方程式をもとに、利益を増やすための施策を考えます。
3. 利益を最大化するためのポイント
MGを5期プレイすることで、以下のような利益向上のポイントが明確になります。
① 価格(P)の戦略的設定
価格が高すぎると売れず、低すぎると利益が出ません。適正な価格を見極めることが重要です。
② 変動費(V)の管理
仕入れコストや生産コストを最適化することで、1個あたりの利益(P – V)を確保します。
③ 販売数量(Q)の拡大
広告や販売戦略を工夫し、販売数量を増やすことでMQ(売上総利益)を向上させます。
④ 固定費(F)のコントロール
固定費を増やしすぎると、MQが増えても利益が出にくくなります。適正な規模での経営を意識することが大切です。
4. 5期のプレイを通じた学び
MGを5期プレイすると、次のような成長を実感できます。
- 短期的な利益ではなく、長期的な利益構造を考える視点が養われる
- 固定費を賄えるだけのMQを確保する重要性が理解できる
- 経営判断の積み重ねが最終利益にどう影響するかを体感できる
5. まとめ
MGを通じて、「利益の本質」は単なる売上の増加ではなく、
- 適正な価格設定
- 変動費のコントロール
- 販売数量の拡大
- 固定費の適正管理
といった要素のバランスによって生まれることを学べます。
次回は「MGの盤上だけじゃない!実際のビジネスに活かす考え方」について解説します!


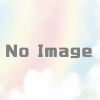
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません